近年、高齢化の影響もあり、ベタニスⓇやベシケアⓇといった過活動膀胱(OAB)の治療薬が処方される機会が増えています。薬局でもよく目にする薬です。よく使われる薬だからこそ、その特徴や違いをしっかり理解することが重要です。例えば、効果の発現時間、持続時間、副作用のリスク、他の疾患との兼ね合いなど、意識すべきポイントは多くあります。そこで今回は、添付文書や最新のガイドラインそして最近開催されたべオーバⓇの勉強会で得た情報をもとに、過活動膀胱治療薬の使い分けについてまとめました。現場ですぐに役立つ情報をお届けしますので、一緒に学んでいきましょう!
- 薬物療法にはβ3受容体作動薬と抗コリン薬がある
- β3受容体作用薬は口渇や認知機能低下という副作用が少ない
- べオーバⓇは生殖器系の警告がなく、ベタニスⓇよりも心疾患系の副作用が少なく、薬物相互作用も少ない。
- 抗コリン薬は尿意を抑える効果が高いが、口渇、便秘、認知機能への影響に注意が必要
- 新しい抗コリン薬の方が膀胱選択性が高く副作用が少ない。
- どの薬が最適かは人それぞれ
下部尿路症状の定義と分類
下部尿路症状とは 下部尿路(膀胱や尿道)に関するさまざまな症状の総称。これらの症状は、以下の3つのグループに分けられる。
1. 蓄尿時症状
膀胱に尿がたまっているときに感じる症状
2. 排尿時症状
実際に尿を出すときに現れる症状
3. 排尿後症状
尿を出し終わった直後に現れる症状
過活動膀胱(OAB)の定義
下部尿路症状の「蓄尿時症状」に分類される。膀胱や神経の働きがうまくいかず、尿をしっかりためられない状態のこと
必須の症状
強い尿意(尿意切迫感)があることが絶対条件。
その他の症状
頻尿:日中の排尿回数が多い(一般的に1日8回以上が頻尿の目安)。
夜間頻尿:夜間に排尿のために起きる回数が増える(通常1回以上)。
切迫性尿失禁:尿意を感じてからトイレに行く前に尿が漏れてしまう。
※尿漏れがなくてもOABと診断される
診断時の注意点
尿路の感染症や局所的な病気がないかどうかをまず確認する必要あり。
診断基準としては、患者さんに質問票に回答してもらう過活動膀胱症状スコア(OABSS)が用いられる。
過活動膀胱症状スコアとは
症状の程度が分かり、治療が必要か判断でき薬やトレーニングでよくなったかをチェックできる。
OABSSの4つの質問
- トイレの回数は多い?(昼間に何回トイレに行くか)
- 夜中にトイレに行くことがある?(寝ている間に何回起きるか)
- 急にトイレに行きたくなることがある?(急な尿意を感じるか)
- 急にトイレに行きたくなって、漏れてしまうことがある?
合計3点以上 → 過活動膀胱の可能性あり
合計5点以上 & 尿意切迫感が2点以上 → 過活動膀胱と診断される
過活動膀胱の治療法
OABの治療は生活習慣の改善(行動療法)と薬物療法が中心。患者さん一人ひとりの症状の程度や健康状態に合わせて治療法を組み合わせる。一般的にはまず生活指導やトレーニングなどの行動療法から開始し、それでも症状がつらい場合に薬を追加する。
それでも十分に改善しない重症例では、神経刺激による治療や手術療法(ボツリヌス毒素の膀胱内注入や仙骨神経刺激療法など)が検討される。
行動療法について
過活動膀胱(OAB)は生活習慣と関係があることが分かっており、生活習慣の改善が治療として推奨されている。
特に体重減少は最も強く推奨(グレードA)されている。
生活習慣の改善として推奨されること
- 体重を減らす(最も効果的)
体重が増えると膀胱への圧力が増し、刺激されやすくなり過活動膀胱を引き起こす。 - 飲み物の調整
カフェインの制限(コーヒー・お茶・コーラなど)
→ エビデンスは低めだが、カフェインを減らすと症状が改善する可能性がある。 - 飲水量の調整
飲水量を25%減らす → 尿意切迫感や排尿回数が減ることが報告されている。
ただし、便秘や尿路感染症のリスクがあるため注意が必要。
個別に医療専門職と相談しながら調整するのが理想的。 - 食事の見直し
低脂肪食が有効(特に閉経後の女性)
低脂肪食の指導を受けたグループでは、尿失禁の回数が減ったという研究結果がある。 - 便秘を防ぐ
便秘があると膀胱を圧迫し、症状が悪化するため、食事や運動で改善を目指す - 座りすぎや下半身の冷えを避ける
長時間座ったままや冷えは症状を悪化させるため、適度に動くことが大切。 - 喫煙の影響
喫煙が過活動膀胱のリスクになるかははっきりしていない。
ただし、20~39歳の女性では喫煙と下部尿路症状が関連していたという研究結果がある
薬物療法
過活動膀胱の薬物療法には大きく分けて抗コリン薬とβ3受容体作動薬の2種類がある
高齢の男性では、前立腺肥大症が原因で過活動膀胱(OAB)の症状が出ている可能性がある。そのため、OABの治療薬であるβ3受容体作動薬や抗コリン薬を使う前に、まずは前立腺肥大症の治療薬であるα1遮断薬やPDE5阻害薬を使うことが考えられる。
明らかな認知機能障害を有する高齢者、あるいは他疾患に対して既に抗コリン作用を有する薬剤を服用している高齢者では、β3受容体作動薬を優先することが望ましいとされている。
| 薬品名 | 推奨度 |
| ベタニスⓇ | A |
| べオーバⓇ | A |
| ポラキスⓇ | B |
| ネオキシテープⓇ | A |
| バップフォーⓇ | A |
| ベシケアⓇ | A |
| ウリトスⓇ | A |
| トビエースⓇ | A |
β3受容体作動薬
膀胱の筋肉にあるβ3受容体を刺激することで、膀胱の筋肉をゆるめる。膀胱の筋肉がゆるむと、尿をたくさんためやすくなる。
その結果、過活動膀胱(OAB)の症状である、急に強い尿意を感じる(尿意切迫感)、トイレが近くなる(頻尿)、急に尿がもれてしまう(切迫性尿失禁) などの症状を改善してくれる。
口の渇きや便秘といった副作用が少ないのが特徴。
現在使われているのはベタニスⓇとべオーバⓇ。
- ベタニスⓇはべオーバⓇに比べ心疾患系の副作用が多い
- べオーバⓇの方が薬物相互作用が少ない
- ベタニスⓇには生殖器の警告があるがべオーバにはない。
1. ベタニスⓇはべオーバⓇに比べ心疾患系の副作用が多い理由
べオーバの方がβ3受容体に非常に選択性が高いから
β受容体にはβ1、β2、β3受容体の3種類がある。主な組織分布は以下の通り
β1受容体 心臓
β2受容体 気管支平滑筋 血管平滑筋
β3受容体 膀胱平滑筋 脂肪細胞
| EC₅₀ | EC₅₀ | EC₅₀ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 薬剤 | β₁受容体 | β₂受容体 | β₃受容体 | β₃受容体選択性(vs β₁) | β₃受容体選択性(vs β₂) |
| べオーバⓇ | >10,000 nM | >10,000 nM | 1.26±0.40 nM | 7,937倍 | 7,937倍 |
| ベタニスⓇ | 594±122 nM | 570±235 nM | 1.94±0.42 nM | 517倍 | 496倍 |
- EC₅₀(半数活性濃度)
→ 生物の半分(50%)に効果が現れる濃度のこと
EC₅₀は薬の強さを比べるのに便利。EC₅₀が低い薬ほど、少ない量で効果が出るので、より強力。
べオーバⓇの方がβ₃受容体に対する選択性が高い(7,937倍)
ベタニスⓇはβ₃受容体に対する選択性がべオーバⓇより低い(約500倍)
→べオーバⓇはβ1・β2受容体にはほとんど結合しないため、心臓や血圧にほぼ影響がない可能性が高い
ただし、実際の臨床試験や市販後調査では、ベタニスⓇもべオーバⓇも有意な心血管リスクの増加は認められていない。
2. べオーバの方が薬物相互作用が少ない理由
べオーバⓇの構造がCYPにくっつきにくい形をしているから
ベタニスⓇはCYP3A4およびCYP2D6で代謝される
ベタニスⓇCYP2D6を阻害するため、CYP2D6で代謝される薬剤(デキストロメトルファン、トリプタノール、ドネペジル)の血中濃度上昇に注意(上昇させる可能性があり)
CYP3A4阻害薬(クラリスロマイシン等)・誘導薬(カルバマゼピン等)の影響を受けるため、併用時は用量調整が必要になる可能性がある
キッセイ薬品から頂いた「高齢OAB患者への適切な治療選択」という資料よりべオーバⓇはCYPを阻害しないし、誘導もしないことが確認されている。
以下にデータを示す。
べオーバⓇの薬物相互作用について
CYP阻害作用(in vitro試験)
- 対象酵素:CYP1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 3A4
- IC₅₀値:>100 μmol/L
- 評価:阻害作用を示さなかった
IC₅₀というのは、薬がどれだけ酵素を邪魔する力が強いかを表す数値。
IC₅₀の数字が小さいほど、少ない量で邪魔する力が強い。IC₅₀の数字が大きいほど、邪魔する力が弱く、ほとんど影響しないという意味。
IC₅₀が100以上という結果は、「べオーバⓇがCYPをほとんど阻害しなかった」ということ。
CYP誘導作用(in vitro試験)
- 対象酵素:CYP1A2, 2B6, 3A4
- mRNA発現量:増大せず
- 評価:誘導作用を示さなかった
「mRNA発現量が増える」=「CYPを作る指令が増える」=「CYPが増えてしまう」ということ。
つまりべオーバⓇはCYPを誘導しなかった
3. ベタニスには生殖器の警告があるがべオーバにはない。
ベタニスには以下の警告がある
生殖可能な年齢の患者への本剤の投与はできる限り避けること。動物実験(ラット)で、精嚢、前立腺及び子宮の重量低値あるいは萎縮等の生殖器系への影響が認められ、高用量では発情休止期の延長、黄体数の減少に伴う着床数及び生存胎児数の減少が認められている。
この理由は
ベタニスⓇとべオーバⓇの化学構造が違う。その違いが、体への影響の違いを生んでいる可能性が高い。
実際に勉強会の際にMRさんに直接質問して教えてもらった内容である。
抗コリン薬
膀胱には、「そろそろおしっこを出そう!」と指令を出すスイッチ(ムスカリン受容体)がある。過活動膀胱の人はこのスイッチが敏感すぎて、まだ膀胱に余裕があるのに「すぐにトイレに行かないと!」と指令を出してしまう。
抗コリン薬は、このスイッチをブロックして、膀胱の暴走を抑えることで、尿意を抑えたり、トイレの回数を減らしたり、尿漏れを防いだりする。
ただし、このスイッチは膀胱以外にも、口や腸、脳にもあるから、口の渇きや便秘などの副作用が出やすい。認知症のリスクが上がる可能性があるとも言われている。特に高齢者では注意が必要。
現在日本で使われている経口抗コリン薬には次のような種類がある
ポラキスⓇ、バップフォーⓇ、ベシケアⓇ、ウリトスⓇ/ステーブラⓇ、トビエースⓇ。作用時間や副作用、投与回数に違いがある。以下の表に主要なポイントをまとめる。
| 薬剤名(一般名) | 特徴(作用時間・選択性など) | 主な副作用 | 適する患者・注意点 |
| オキシブチニン(ポラキスⓇ 他) | 最も古い抗コリン薬。即効性だが作用時間短め(1日3回投与)。 経皮吸収型テープ剤(ネオキシテープⓇ)もあり。 | 副作用が強く出やすい(口の渇き、認知機能への影響など) テープ剤は皮膚刺激がありうるが口渇少なめ。※1 | 内服は高齢者には向いていないと言われている。 テープ剤は副作用が少なく、高齢者でも使いやすいとされている。 |
| プロピベリン (バップフォーⓇ) | 抗コリン作用に加え平滑筋に対するカルシウム拮抗作用を併せ持つ※2 1日1〜2回投与 | 副作用少なめ | 尿漏れ(混合性尿失禁)にも使われることがある。 |
| ソリフェナシン (ベシケアⓇ) | ムスカリンM3受容体にしっかり効くので、膀胱に選択的に作用する。 1日1回投与(作用時間長く服用しやすい)。ベシケアⓇのM3選択性について | 副作用が比較的少ない。 認知機能への影響が少ないとされている。 | 腎不全や肝障害では投与量上限に注意(添付文書参照)。 |
| イミダフェナシン (ウリトスⓇ 等) | M3受容体選択性が高い 半減期約3時間と短く1日2回投与。 膀胱選択性が高い一方、中枢移行性が低く認知機能障害に与える影響が少ない。※4 | 飲み薬の中では口の渇きが最も少ないと言われている。 | 夜間頻尿や睡眠の質も改善する効果があるという報告も |
| フェソテロジン (トビエースⓇ) | 膀胱に選択的に作用する | 抗コリン系副作用は用量依存的(8mgでは4mgより口渇・便秘増加)。 | 高齢者に特に向いている薬(認知機能への影響が少ない、薬の安全性を評価するシステム で、過活動膀胱の薬の中で唯一「高齢者にも使いやすい」と認められた薬 ) |
M1受容体への作用は認知機能低下のリスクがあるため、避けられる傾向がある
M2受容体への作用は心臓への副作用(頻脈など)のリスクがある
M3受容体は膀胱収縮に直接関与するため、過活動膀胱治療薬の主要ターゲット
※1
ポラキスⓇは経口投与後、肝臓でデスエチルオキシブチニン(DEO)という代謝産物に変換される。DEOは強い抗コリン作用を持ち、口渇などの副作用の主な原因とされている。
ネオキシテープⓇは、皮膚から直接血管に吸収されるので肝臓を最初に通らない。つまりDEOの産生を抑え、副作用を軽減する。
※2
膀胱の筋肉が過度に収縮するのを防ぐ効果がある
※3
M1受容体は主に脳(海馬・大脳皮質)に存在し、記憶や認知機能に関与している。なのでM3選択性が高いソリフェナシンはポラキスよりは認知機能を低下させにくい。
※4
抗コリン薬の中でポラキスⓇは脂溶性が高く、BBB を通過しやすいため、認知症患者には勧められない。一方ウリトスⓇ などの新しい OAB 治療薬は、比較的 BBB を通過しにくいと考えられる。
抗コリン薬の半減期
| 薬剤名 | 半減期(T1/2) |
| ポラキスⓇ | 約1時間 |
| バップフォーⓇ | 約14時間 |
| ベシケアⓇ | 約38時間 |
| ウリトスⓇ | 約3時間 |
| トビエースⓇ | 約10時間 |

抗コリン薬が増えると、認知症・転倒・骨折のリスクが高くなるから併用薬を注意することが重要だよ。
よくある質問
Q1 抗コリン薬とβ3受容体作動薬、どちらの薬がいいの?
副作用が少ないのがいい → β3受容体作動薬
尿意をしっかり抑えたい → 抗コリン薬
どちらか一つでは効果が弱い場合 → 両方を併用することもある
Q2 β3作動薬が効果不十分な場合の変更の効果は?
ベタニスⓇ → べオーバⓇ C1
べオーバⓇ → ベタニスⓇ C1
抗コリン薬を追加する C1
推奨グレードの意味
A 行うよう強く勧められる
B 行うよう勧められる
C 行うよう勧められるだけの根拠がない
C1 行ってもよい
C2 行うよう勧められない
Q3 抗コリン薬が効果不十分や副作用がひどく変更したい場合は?
副作用がひどい場合
抗コリン薬 → 抗コリン薬 C1
抗コリン薬 → β3受容体作動薬 B
副作用(口の渇き・便秘)が減る可能性が高い。(エビデンスがしっかりしている)
効果不十分
抗コリン薬 → β3受容体作動薬 C1
OABの症状改善の効果は、抗コリン薬と同程度。
Q4 抗コリン薬とβ3受容体作動薬との併用は
ベシケアⓇ服用し効きが悪い。ベタニスⓇを追加する A
ベタニスⓇ服用し効きが悪い。抗コリン薬(ベシケアⓇ5mg、バップフォーⓇ20mg、ウリトスⓇ0.2mg)追加 B
ベシケアⓇ以外の抗コリン薬を使っていて効きが悪い。ベタニスⓇ追加 C1
べオーバⓇや抗コリン薬を使っていて効きが悪いときこの2つを併用する C1
Q5 混合性尿失禁(切迫性尿失禁+腹圧性尿失禁)の治療には薬が効くのか?
トレーニング+薬でかなり改善できる
抗コリン薬(ベシケアⓇ・バップフォーⓇ)やベタニスⓇは、尿もれを減らすのに効果がある。A
ベタニスⓇは特に尿もれに効果があり、約半分の人で尿もれがなくなった。
Q6 抗コリン薬で副作用が起こった時は?
副作用がつらいときは、薬を減らすか変更するのが基本.
口の渇きには、マッサージ・保湿・ガム・酸っぱい食べ物が効果的!
便秘には、水分・食物繊維・腸のマッサージ・ヨーグルトが役立つ!
皮膚のかゆみは、貼る場所を変える&保湿クリームで予防できる!
以上、過活動膀胱についてまとめました。
日々のご相談対応や服薬指導の場面で、少しでも参考になれば嬉しいです。
最後までお読みくださりありがとうございました。


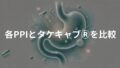
コメント