年に一度の健康診断。最近では「ピロリ菌検査を受けた」と話す患者さんも珍しくなくなりました。ピロリ菌が胃にすみついていると、慢性胃炎や胃潰瘍、さらには胃がんのリスクが高まることがわかっており、早期の発見と除菌がとても重要です。
2013年に除菌治療の保険適用が拡大されて以降、薬局でもボノサップやボノピオンなどの除菌薬を調剤する機会が増えてきました。服薬指導の際には、下痢に関する注意喚起は広く知られており、多くの薬剤師が伝えていると思いますが、それ以外にも指導のポイントはいくつかあります。たとえば、除菌を成功させるためには、決められたとおりに薬をきちんと飲みきることが非常に重要です。途中で飲み忘れたり、中止してしまうと除菌が失敗し、耐性菌のリスクも高まります。さらに、除菌期間中の飲酒の影響や、除菌後の再検査の時期など、押さえておきたい点は意外と多いのです。
この記事を読むと、薬剤師として知っておくべきピロリ菌除菌の基礎知識と、患者さんへのわかりやすい説明のコツが分かります。現場でそのまま活用できる内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
ピロリ菌と胃がんの深い関係

1994年、WHOはピロリ菌を「確実な発がん因子」と認定した。
長期間ピロリ菌に感染していると、胃の粘膜が弱って薄くなり(萎縮)一部が腸のような性質に変わってしまう(腸上皮化生)。
これが胃がんリスクを大きく高めることになる。
日本の10年間の調査
| 区分 | 対象人数 | 胃がんになった人数 | 胃がんの割合 |
|---|---|---|---|
| ピロリ菌に感染していない人 | 280人 | 0人 | 0% |
| ピロリ菌に感染している人 | 1246人 | 36人 | 2.9% |
ピロリ菌感染者の胃がん発生率は2.9%である。
一方、非感染者では0%という結果が出ている。
ピロリ菌除菌で胃がんリスクが低下
ピロリ菌感染が胃がんの最大リスク因子である。
このピロリ菌を薬で除菌すると、胃がんになる危険性が、約半分減ることが、日本のたくさんの研究で分かっている。
📚参考 科学的根拠に基づくがんリスク評価とがん予防ガイドライン提言に関する研究
2013年2月より前
胃潰瘍や十二指腸潰瘍、胃がん治療後など限られた疾患のみが保険適用
2013年2月から
ピロリ菌による「慢性胃炎」に対する除菌治療が健康保険の適用
保険適応拡大により1,000万人以上が除菌治療を受けている。(~2020年)
その結果胃がんで亡くなる人の数は減少傾向にある。
2010年
約5万人
➡︎
2022年
約4万人
約1万人減少した。
WHO(世界保健機関)もピロリ菌を除菌することで胃がんを予防できると認めていて、世界中の国々に対して「対策を立てましょう」と呼びかけている。
若いうちの除菌が効果的
日本ヘリコバクター学会の最新ガイドライン(2024年版)によると
若いうちに除菌することが非常に有効。
- 理想は20〜30代、遅くとも50歳までの除菌が望ましい
- 中学生以上の無症状者にも検査・除菌治療を推奨
- 未成年者への除菌は「弱い推奨」ながら、重い副作用の報告はない
感染経路
感染経路はまだはっきりとは分かっていないが、最近の研究からは口から入れば感染することは確実と考えられている。
ピロリ菌は、ほとんどが乳幼児(5歳以下)に感染すると言われている。これは、幼児期の胃の中が酸性が弱く、ピロリ菌が生き残りやすいためと考えられている。
疑われている経路は母から子への家庭内感染(食べ物の口移しなど)。
現代の日本では上下水道が整備されているため、生水からの感染や成人後の日常生活での感染はほとんどないと考えられている。
除菌治療の流れ

1. 対象となる疾患の確認
以下のいずれかの疾患と診断されている方が対象となる。
🔸胃潰瘍または十二指腸潰瘍
🔸胃MALTリンパ腫(胃の中のリンパ組織にできるがん)
🔸特発性血小板減少性紫斑病(血小板が少なくなる病気)
🔸早期胃がんに対する内視鏡的治療後胃
🔸内視鏡検査で診断された胃炎 ※内視鏡検査が必須
2. ピロリ菌検査
ピロリ菌の検査方法には、内視鏡を使う方法と使わない方法がある。
内視鏡を使う検査方法(組織採取が必要)
- 迅速ウレアーゼ試験
(採取した胃組織にウレアーゼ反応を使って判定) - 鏡検法(組織鏡検法)
染色した組織を顕微鏡で観察し、ピロリ菌を直接確認 - 培養法
採取した組織からピロリ菌を培養して増やし、性質を詳しく調べる - 核酸増幅法 (PCRなど)
採取した組織からピロリ菌のDNAを検出
内視鏡を使わない検査方法
- 抗体測定(血液検査)
- 尿素呼気試験(息を吹き込む検査)
- 便中抗原測定(便を採取する検査)
3. 一次除菌
ピロリ菌陽性と診断されたら、一次除菌として以下の3剤を7日間服用する。
- PPI又はP-CAB(タケキャブ):胃酸分泌を抑える薬
- アモキシシリン:抗菌薬
- クラリスロマイシン:抗菌薬
PPIが必要な理由
胃酸を抑えることで、抗生物質(特にアモキシシリン)が胃酸で分解されることを防ぎ、効果を最大化する。
正しく服用すれば、一次除菌の成功率は77.3~93.3%です。
📚参考 先進医療ネット
4. 二次除菌(一次除菌が失敗した場合)
一次除菌が失敗した場合は、二次除菌として以下の3剤を7日間服用する。
- PPI又はP-CAB(タケキャブ)
- アモキシシリン
- メトロニダゾール(クラリスロマイシンに替えて使用)
クラリスロマイシンではなくメトロニダゾールを使用する理由
一次除菌の失敗はクラリスロマイシン耐性菌の可能性が高いため。クラリスロマイシン耐性の頻度は年々増加しており、2013〜2014年の調査では38.5%にも達している。
ピロリ菌除菌における注意点

アルコールの制限
一次除菌
アルコールはできるだけ控える
理由: アルコールにより胃酸分泌が促され、せっかくPPIで抑えた胃酸の効果が低減する
二次除菌
アルコールは厳禁!
理由:メトロニダゾールはアルコールの代謝に関わる酵素を阻害するため、アルコールが体内で分解されにくくなり、少量の飲酒でも強く酔ったような状態になることがある。
📚参考 福岡県薬剤師会
飲み忘れに注意
政府系サイトや製薬メーカーの公式情報では、飲み忘れによる除菌率の具体的な低下数値は書かれていないが、服薬遵守の重要性が強調されている。日本ヘリコバクター学会のガイドラインや複数の文献でも、服薬遵守が除菌成功の最も重要な因子であるとされている。
例えば、ある研究では服薬遵守率が60%未満の場合、除菌率が96%から69%に低下したと報告されており、別の研究では服薬遵守率が80%未満の場合、除菌率が85-94%から39-53%に低下したと報告されている。
📚参考 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3002536/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10388557/
除菌後の判定検査
除菌後の判定検査は、除菌終了から4週間以上あけて実施する必要がある。
これには重要な理由がある。
- 除菌直後は菌が一時的に減少しており、実際は陽性でも陰性と判定される可能性(偽陰性)がある。
- PPI(胃酸を抑える薬)の影響で菌の活動が抑えられ、検出されにくくなる。このため、検査前は少なくともPPIを2週間以上休薬する必要がある。
患者さんへの説明ポイント

服用方法と重要性
- 朝・夕の1日2回、3種類の薬を一緒に服用
- 7日間、飲み忘れなく服用することが除菌成功の鍵
- 飲み忘れると除菌率が大幅に低下
アルコール制限
- 一次除菌:できるだけ控える
- 二次除菌:厳禁
副作用
- 下痢や軟便が起こることがある
- 味覚異常が出ることもある
- 重い副作用(発熱、発疹など)が出たら速やかに受診
除菌後の検査
- 除菌後4週間以上経ってから検査を受ける
- 検査前2週間はPPIを中止する必要がある
- 検査で除菌成功を確認することが重要
胃がん予防の意義
- 除菌成功で胃がんリスクが低下
- 若いうちの除菌ほど効果的
まとめ
ピロリ菌除菌は胃がん予防の観点から非常に重要な治療である。正しい知識を持って除菌治療に取り組むことで、高い除菌率と胃がん予防効果が期待できる。
- 胃がん予防: 除菌によって胃がんリスクが低下
- 若年での除菌: できるだけ若いうちの除菌がより効果的
- 服薬の徹底: 7日間の飲み忘れのない服用が除菌成功の鍵
- アルコール制限: 一次除菌では控え、二次除菌では厳禁
- 除菌後の検査: 必ず4週間以上あけて検査を受ける
ピロリ菌の検査をする人が増え、薬局でも除菌薬を調剤する機会が増えています。除菌することによって胃がんのリスクが減るので、除菌薬についての説明だけではなく、胃カメラやピロリ菌検査をすすめることも薬剤師として重要だと感じています。
そして除菌といえば下痢や軟便の副作用ばかり注意してしまいがちですが、アドヒアランスも大切なので、除菌薬お渡し時に飲み忘れると除菌率が落ちることも忘れずにお伝えしたいですね。
最後までお読みくださりありがとうございました。日々の業務のお役に立てれば嬉しいです。
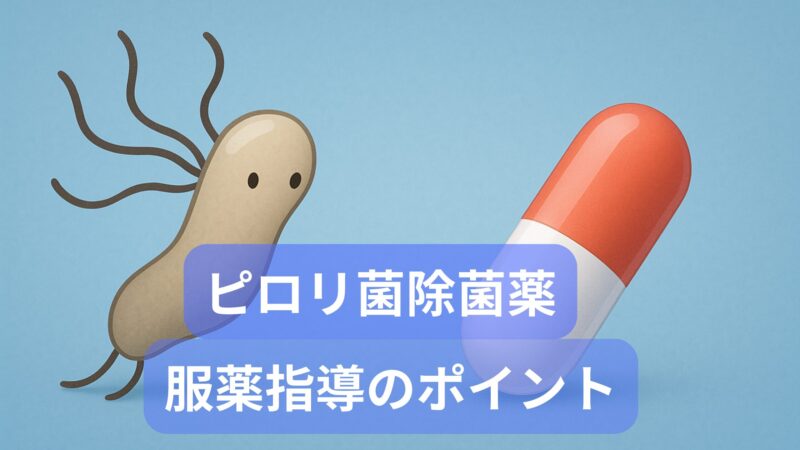

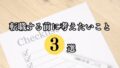
コメント