日本はますます高齢化が進み、認知症の患者さんの数も年々増えています。なかでもアルツハイマー型認知症に伴う「攻撃的な言動」や「過活動」は、介護されるご家族やスタッフにとって大きな負担となってきました。これまで、リスパダールⓇなどが適応外で使われることが多かったのですが、2024年ついに新たな選択肢が登場しました。
それが「レキサルティⓇ」です。日本で初めて、アルツハイマー型認知症に伴う攻撃性や過活動に対して正式に承認されたお薬として、今、現場でも注目を集めています。
私の勤める薬局でも、最近このレキサルティⓇを処方される方が増えており、介護の現場に小さくても確かな変化の兆しを感じています。
今回は、このレキサルティがどのようなお薬なのか、その特徴や期待される効果について、わかりやすくご紹介していきます。
- 日本で唯一「アルツハイマー型認知症に伴う焦燥感、易刺激性、興奮に起因する、過活動または攻撃的言動に適応を持つ
- 抗精神病薬に比べ副作用が少ないので高齢者に使いやすい
- 副作用としては、アカシジアや体重増加が比較的多く見られる
なぜ攻撃的になるの?脳の中で起きていること
アルツハイマー型認知症では以下のような問題行動(BPSD)が出ることがある
- 焦燥感(そわそわして落ち着かない)
- 易刺激性(すぐ怒る)
- 興奮(暴言や暴力)
これらは、脳の「ブレーキ」がうまく働かないことが原因である。
もう少し詳しくいうと
1.脳内のしくみの変化
2.神経伝達物質のバランスの乱れ
この2つが重なって、感情のコントロールがうまくいかなくなり、攻撃的な言動につながる。
1.脳内のしくみと変化
前頭前野機能(実行制御)
→たとえば「カッとなっても怒鳴らずに我慢する」ような制御をする部分。
認知症で機能が低下(=抑制が弱まる)
扁桃体機能(情動衝動)
→ 怒りや不安、恐怖など感情を作る場所。
この部分が過剰に反応すると、興奮しやすくなる。
2. 神経伝達物質のバランスが崩れる
各神経伝達物質の作用
ノルアドレナリン
- やる気が出る。集中力が上がる。危機に対応しやすくなる。
- 緊張やストレスに反応する
- 心拍数や血圧を上げる
- 注意力や集中力を高める
セロトニン
- 心の安定・リラックス
- 気分を安定させる
- イライラや不安を抑える
- 睡眠や食欲にも関わる
ドパミン
- 快感・ごほうび・やる気
- 楽しい・うれしいと感じる
- 意欲ややる気を引き出す
- 達成感や学習にも関与
アルツハイマー型認知症に伴うイライラや落ち着きがない場合
ノルアドレナリンが過活動
→不安・混乱・ストレスが増え、興奮しやすい、怒りっぽい、攻撃的、落ち着きがないなどの行動が出ることがある
セロトニンが機能低下
→気分をなだめる力が弱まり、イライラや落ち込みが起こりやすくなる
ドパミン調節障害
→ 必要なときに必要な量のドパミンを出したり止めたりできない状態。興奮して攻撃的になる人もいれば逆にやる気がなくなって何も話さない人もいる
BPSDはまず薬以外の治療法(リハビリ、心理療法、環境調整)をする。
これをやってもダメな場合は薬物療法を行う。
レキサルティⓇ、待望の新適応!
○統合失調症
○うつ病・うつ状態(既存治療で十分な効果が認められない場合に限る)
○アルツハイマー型認知症に伴う焦燥感、易刺激性、興奮に起因する、過活動又は攻撃的言動
作用機序
レキサルティは3つのモノアミン(ノルアドレナリン、セロトニン、ドパミン)に少しずつ作用して、ちょうどいいバランスに整えてくれる薬である。
① セロトニン(5-HT)
- 5-HT₁A受容体 → 部分アゴニスト(やさしく刺激)
この部分アゴニストというのは、完全にスイッチを入れるわけではなく、「ちょっとだけONにする」イメージ。
5-HT₁A受容体は「ブレーキ役」。セロトニンが出すぎないように抑える働きがある。
セロトニンを出しすぎるとイライラや不安が強くなるから、やさしくブレーキをかけて不安をやわらげたり、落ち着かせたりする。 - 5-HT₂A受容体 → アンタゴニスト(ブロック)
5-HT₂A受容体は脳の興奮、幻覚、不安、睡眠などに関わっている。この受容体が過剰に刺激されると、幻覚や不安、不眠につながることがある。
つまりブロックすることで、気分を落ち着かせたり、不安を和らげる作用がある。
② ドパミン(DA)
- D₂受容体 → 部分アゴニスト(やさしく刺激)
「ドパミン」は、やる気、喜び、運動、気分などに関係している。
D₂受容体にドパミンがくっつくと、「やる気が出る」「体が動く」などの信号が出る。
ドパミンが多い場合
ドパミンが多すぎると、受容体が強く刺激されすぎてしまい、幻覚や興奮などの症状が出ることがある。そこにレキサルティが登場すると、ドパミンより先に受容体にくっつく。でもレキサルティはドパミンほど強い刺激は与えない(=部分アゴニストだから)。
その結果、強すぎた刺激がゆるやかになり、興奮などの症状がおさまる方向に働く。
ドパミンが少ない場合
ドパミンが少ないと、脳の「やる気スイッチ」がまったく押されていないような状態になる。
そんなときにレキサルティが来ると、このスイッチを軽くポンと押してくれるような働きをする。 そのおかげで、脳は少し目を覚ましたようになり、やる気が出たり体が動きやすくなったりする。
まとめると、興奮しすぎを抑えつつ、やる気や集中力を保つバランスをとる働きがある。
③ ノルアドレナリン(NA)
- α₂C受容体 → アンタゴニスト(ブロック)
- α₁B受容体 → アンタゴニスト(ブロック)
α₂C受容体をブロックする作用(ブレーキ解除で元気アップ)
α₂C受容体とは、脳の中でアドレナリン(元気ややる気に関係する物質)が出すぎないようにする『ブレーキ役』です。
普段はアドレナリンが出すぎないように抑えています。
レキサルティはその『ブレーキ』を少し外す薬。
つまり、気分が落ち込みすぎたり、元気がなくなりすぎたりするのを防ぐ。
α₁B受容体をブロックする作用(興奮をおさえる作用)
α₁B受容体は、血管や脳にあって、アドレナリンなどがくっつくと興奮したり、イライラが強くなる。
レキサルティはこのスイッチをブロックする。
つまり、興奮やイライラが起きにくくなり、心が落ち着いて穏やかになるのを助ける。
まとめると、レキサルティⓇはイライラや不安が強すぎるときはそれを落ち着けて、元気がなくて落ち込んでいるときには意欲を出してくれる
| 神経伝達物質 | 受容体 | レキサルティの作用 | 効果のイメージ |
| セロトニン(5-HT) | 5-HT₁A | やさしく刺激 | 不安を抑える |
| セロトニン(5-HT) | 5-HT₂A | ブロック | 興奮を抑える |
| ドパミン(DA) | D₂ | やさしく刺激 | やる気や集中力を保つ |
| ノルアドレナリン(NA) | α₂C、α₁B | ブロック | イライラ・攻撃性を抑える |
エビリファイⓇとの比較
レキサルティⓇと似た薬にエビリファイⓇがあるが、この2つの薬の違いは、
- レキサルティⓇの方がセロトニンに対する効果が強く、気分を整える効果がより高い。
- ドパミンに対しては、エビリファイⓇより刺激が弱く、優しい効く。
つまり、レキサルティⓇはエビリファイⓇよりも脳の興奮を抑える力がマイルドで、気持ちを安定させる力が強い薬と言える。
副作用
今までの抗精神病薬は副作用が多かった。
D2受容体遮断
→ 手や顔が勝手に動く(錐体外路症状)
→誤嚥性肺炎
α1受容体遮断
→ 立ちくらみなどの過鎮静
→転倒や骨折
H1受容体
→ 食欲が増える
→ 体重増加、脂質異常
→心臓や血管の病気
レキサルティは必要以上にドパミンを止めないから、副作用が少ないかもしれない
イメージとしては
抗精神薬はブレーキを強く踏んで止める(=副作用が出やすい)
レキサルティはブレーキとアクセルをうまく使って調整する(=副作用が出にくい)
効果
聞き取り
介護者、医師どちらも主観的な改善を感じられた。
介護者は2mg、4週間目から有意差あり
医者は1mg、2mgともに2週間目から効果あり
CMAIを使った評価
CMAIはアルツハイマー型認知症の人が見せる「落ち着きのなさ」や「怒りっぽさ」などの行動を、どのくらいの頻度で起きるかを確認・評価するためのもの
行動は3つの因子(カテゴリー)に分けられる。
【因子と行動の例】
| 因子 | 内容 | 行動の例 |
| Factor 1 | 攻撃行動(身体・言語) | たたく、押す、ひっかく、悪態をつく、暴言、叫ぶ |
| Factor 2 | 非攻撃行動(身体) | 歩き回る、服を脱ぐ、物を乱暴に扱う、同じことを繰り返す |
| Factor 3 | 非攻撃行動(言語) | 不満を言う、繰り返し要求、拒絶的な発言、意味のない繰り返し話 |
| その他 | 上記に当てはまらない行動 | 物を壊す、奇声、性的言動など |
【評価方法】
行動の頻度を7段階でスコア化
- 一度もなかった
- 週1回未満
- 週に1~2回
- 週に数回
- 1日に1~2回
- 1日に数回
- 1時間に数回
10週目に2mgでは全てのFactorで有意差をもって減少させた。
10週目に1mgはFactor 1とFactor 3において有意差をもって減少させた。
用法用量
1日1回0.5mgから開始した後、1週間以上間隔をあけて1mgに増量。さらに1週間あけて2mgに増量可能。
有効容量は1mg2mg
2mgは効果が高い一方で、副作用のリスクも上がるため注意が必要
食事の影響を受けない
副作用
アカシジアと体重増加が多い。
アカシジア
- 足をゆすってしまう
- 座っていられずに立ち上がってしまう
- 体がソワソワして落ち着かない
ドパミンの刺激が中途半端 → 脳が混乱 → ソワソワして落ち着かない
体重増加
エビリファイⓇとの比較でも述べたが
H1受容体を遮断する → 食欲が増える → 体重増加
以上、レキサルティⓇについてまとめてみました。
レキサルティⓇは、これまでの抗精神病薬と比べて副作用が比較的少なく、特に高齢者にも使いやすいお薬であることから、薬局での服薬指導や薬歴記載の際にも知っておきたい薬剤の一つだと思います。
この記事が、日々の調剤業務や患者さん対応の参考となり、少しでもお役に立てれば嬉しく思います。
最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。


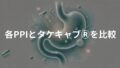
コメント